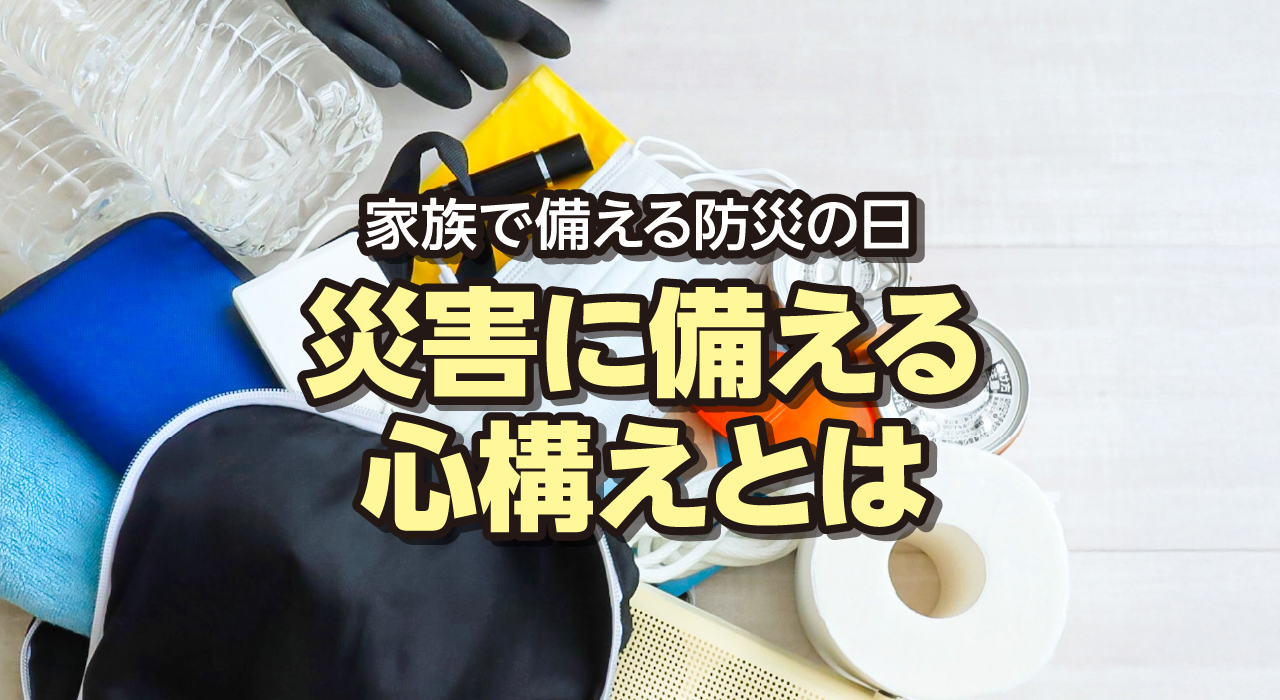1923年9月1日に起きた関東大震災を忘れないために、災害に備えることを目的として、国が「防災の日」を定めました。
地震、雷、火事、親父だけでなく、近年では、災害に40度を超える酷暑や雨の恵みがない干ばつも含まれるようになりました。
私たちは、川や池、海、木々の中で遊び、眺め、癒され、また田や畑では食べ物を育てるなど、自然の恵みを受け、共に暮らしています。しかし、その自然が災害を引き起こし、私たちの暮らしを壊してしまうこともあります。その両面を知ったうえで生きていく心構えが必要です。
被害をイメージし、備えましょう
災害時にどのような被害が及ぶかを普段から考えておくことが大切です。自分の住む町がどのような被害を受けやすいのか、災害の種類によって違いがあることをイメージしてみませんか。
避難訓練で机の下に隠れる動作や、防災頭巾のかぶり方などを実際に練習し、体で覚えておくことも重要です。とっさのときに考えずに動けるようになるからです。子どもの頃の記憶に頼るのではなく、今の身体の状態を考えた体験が必要です。たとえば、腰や肩の痛みで机の下に潜るのが難しくなっているかもしれません。どうすればスムーズに避難できるかを今の自分に合わせて身体を動かしてみることが大切です。
備えた防災グッズは使って、慣れること
防災用品は中身を点検し、何を用意しているか、どんな時に使うのか、その使い方も確認しておきましょう。非常食も試食してみて、味に慣れておくことが大切です。賞味期限の確認や調理方法、アレンジの工夫なども、在宅避難のシミュレーションになります。たとえば、今夜の夕食を非常食にしてみるのも、よい体験になるかもしれません。使った分はすぐに補充すれば、ローリングストックにもなります。こうした行動からの学びは、防災において非常に役立ちます。
家族で実践、我が家の防災訓練
ペットも含めて、家族で「我が家の防災訓練」をしてみましょう。最寄りの避難所まで実際に歩いてみることで、その道中にどんな危険があるかを確認できます。昼間だけでなく、停電時を想定して夜間にも歩いてみると、昼とは異なる気づきがあるはずです。暗がりでは小さな段差も危険に感じられるかもしれませんし、不安感が増すこともあるでしょう。
ニュースで見るだけでなく、我が家の「防災訓練の日」として、今日できることから少しずつ始めてみませんか?