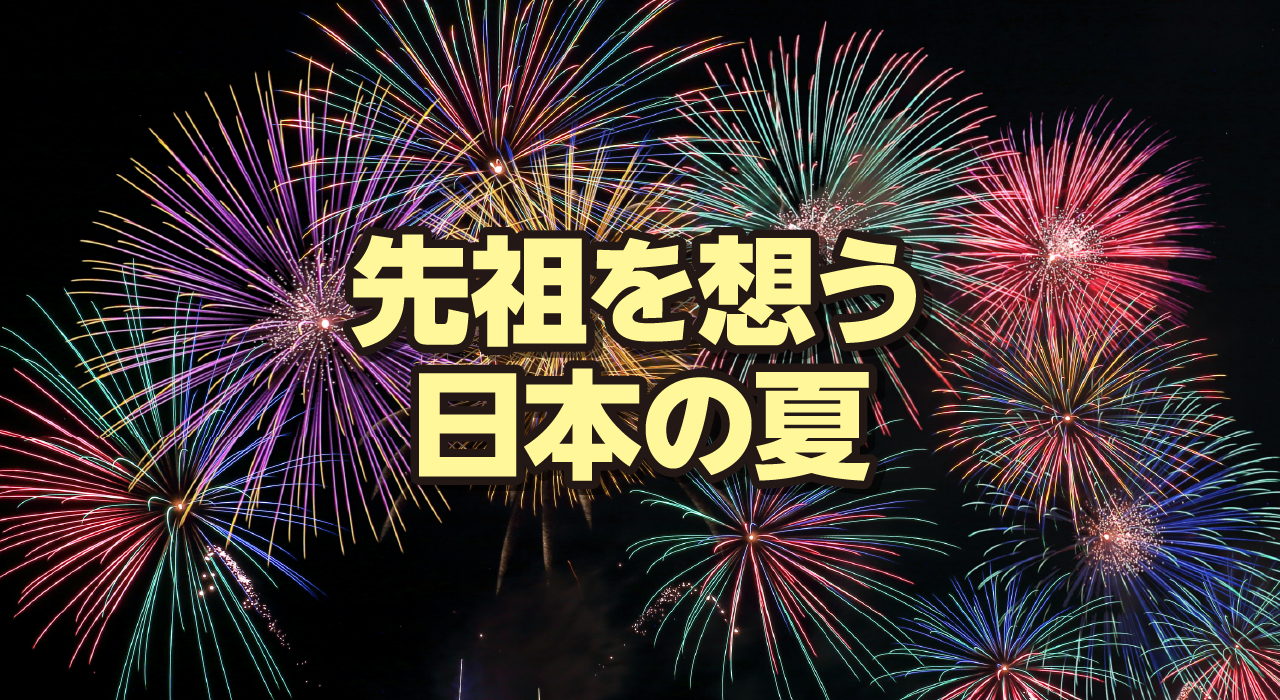お盆(正式名称「盂蘭盆会(うらぼんえ)」)は、語源をサンスクリット語の「ウランバナ(逆さ吊りの苦しみを救う)」に持つとされています。
日本の伝統的な仏教行事のひとつで、先祖の霊を迎えて供養する期間のことを指します。
お盆の時期と過ごし方
一般的には8月13日~16日のお盆がおこなわれます(旧暦の名残を太陽暦に合わせた日程です)。地域によっては、今も旧暦の7月13日~15日を基準にしているところもあります。
亡くなった方の霊がこの世に帰ってきて、家族とともに過ごす大切な時間です。
地域ごとの風習
全国各地で、多様なお盆の風習が見られ、そのかたちは地域ごとに異なります。
・東北:精霊馬(しょうりょううま)として、ナスやキュウリで作った馬や牛を飾る
・関西:京都の五山送り火(大文字焼)、奈良の郡山おどり
・四国:徳島の阿波踊り
・九州:長崎の精霊流し
・沖縄:旧暦7月13日~15日に行われ、エイサー踊りで先祖の霊を慰め、送り出す など。
お盆のしつらいと意味
「しつらい」とは、供養の場を整えることを指し、お盆ならではの飾りや準備にも意味があります。
こころの灯をつなぐ 先祖を敬い、思う気持ちを大切にしたいですね。あなたの大切な家族が、ひとときの「帰り」を待っています。そうした情景は、歌人たちの詩にも詠まれています。
俳句に詠まれたお盆の情景
送り火や 船に積み込む 野のあかり ― 正岡子規
蚊帳吊るして 昼寝せうもの 踊の後 ― 松尾芭蕉
盆東風や 波に小舟の 漕ぎかくれ ― 与謝蕪村
迎え火を 焚きし門より 風生まれ ― 高浜虚子
お盆の灯の 中を子供が 走って行く ― 種田山頭火
あなたがいてくれたから、私が今ここにいます。深謝、合掌。