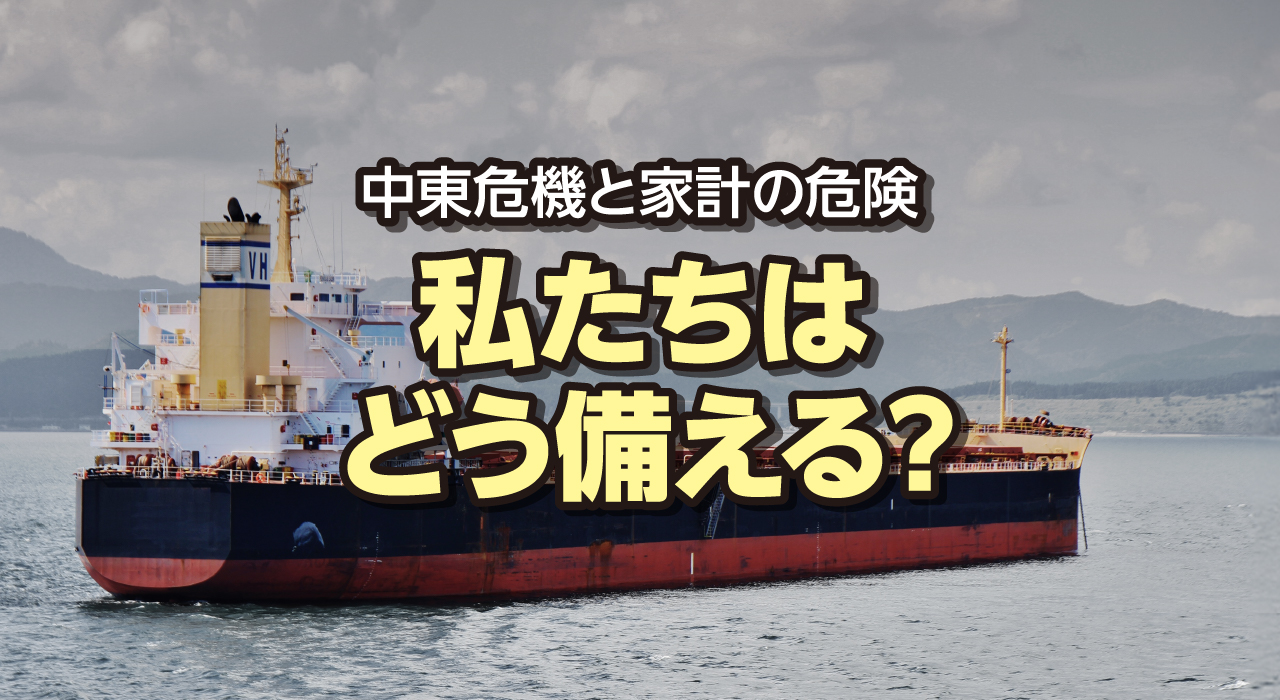2025年6月13日、イスラエル軍がイランを攻撃し、イラン側も応戦しました。両国による攻撃の応酬が続く中、22日には米軍がイランの核施設を空爆しました。これを受けてイランは報復措置として、ホルムズ海峡の封鎖を国会で承認。6月24日に一時的な停戦合意に至りましたが、依然として緊張状態が続いています。
ホルムズ海峡と日本のつながり
世界で取引される原油のおよそ3割、液化天然ガスの約2割がホルムズ海峡を通過しています。日本は中東からの石油に大きく依存しているため、この海峡が封鎖され原油が入手できなくなれば、深刻な打撃を受けます。
電気やエネルギーの影響が身近に
発電に必要なエネルギーの調達が困難になれば、電力供給が不十分となり、電気代のさらなる高騰を招き、家計を圧迫します。電力不足が深刻化すれば、大規模停電に発展する可能性もあります。6月の時点ですでに厳しい暑さが続いており、夏本番に大規模停電が発生すれば、命に関わる事態になりかねません。
また、ガソリン価格の高騰は、自家用車の移動だけでなく、物流業界のコスト増加を招きます。輸送費の上昇は商品の価格に転嫁され、食品や日用品、輸入品の価格も上昇します。石油由来のプラスチックや合成繊維、肥料などの原材料供給も不安定になり、食品トレーやペットボトル、ビニール袋、プラスチックスプーンといった食品関連製品の価格も上がります。深刻な供給不足が生じれば、「○○ショック」と呼ばれるような社会的混乱が起きる可能性があります。
家計や仕事にも広がる影響
企業もエネルギーコストの上昇により収益が減少し、賃金を上げられず、雇用の維持が難しくなります。株価は下落し、貿易赤字の拡大から為替市場では円安が進行し、輸入品全般の価格がさらに上昇するという悪循環に陥ります。中東の不安定化は、世界経済全体を揺るがす要因となり、投資の冷え込みや金融市場の混乱を通じて、家計や雇用にも波及していきます。
今からできる小さな備え
私たちがこのような事態に備えるとすれば、電気やガスなどエネルギーの使用量を抑えること、そして日用品や食料品を備蓄しておくことが挙げられます。日本は国家レベルでも家庭レベルでも自給自足率が低く、特定の国や地域に依存しすぎることでリスクが高まっています。
地元で支え合う暮らしへ
令和という時代は、もしかすると貨幣経済からの転換期なのかもしれません。電気や食品を地産地消でまかなう、自給自足型のライフスタイルで備える。循環型社会やSDGsは、遠い未来の話ではなく、今そこにある現実の課題なのです。
お金に頼るだけでは立ち行かない非常時に備え、食品やライフラインを家庭や地域で確保し、支え合える体制を築くことが求められます。それは、かつての江戸時代の長屋文化を思わせる姿かもしれません。