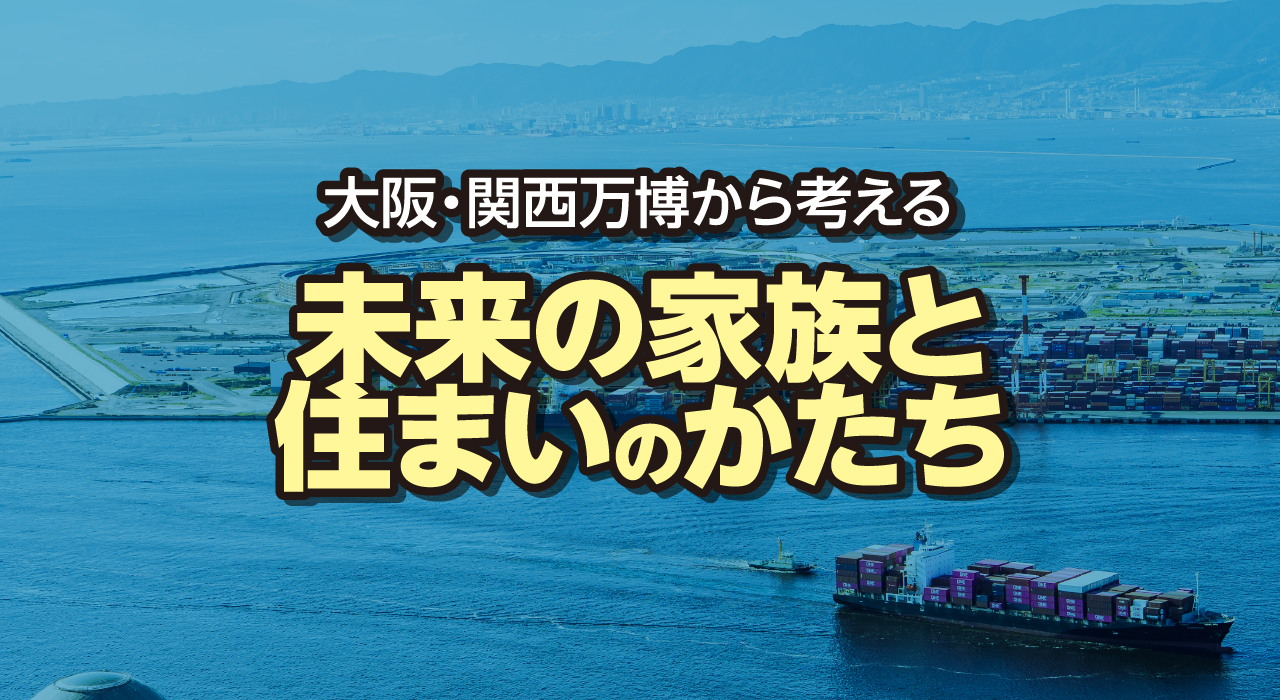大阪関西万博の一般入場者数が4月までに100万人を超えました。その7割以上が50歳以上と推計されていることが、スマートフォンの位置情報を分析する会社「クロスロケーションズ」の調査で分かりました。万博協会によると、日別では開幕日の12万4,339人が最多ですが、半年間で想定する2,820万人を達成するために必要な1日平均15万人には一度も届いていません。今後、来場者を増やすには、10月13日までの開催期間中に子育て世代の呼び込みがカギを握りそうです。
万博に込められた理念と歴史
愛知万博では、目標の1,500万人を上回る2,200万人が来場しました。55年前の大阪万博では、6,400万人という驚異的な入場者数を記録しています。
会場建設費が当初の2倍に膨らんだ現在、入場者数の増加は欠かせない状況です。しかし、SF作家・小松左京氏が提唱した「万国博覧会は、様々な矛盾を解決する知恵と技術を発見するための手段であり、博覧会自体が目的ではない」という考え方に沿えば、その道標は今も胸に響きます。当時、太陽の塔を制作した岡本太郎氏や、会場設計を担当した丹下健三氏など、日本を代表する専門家たちの情熱が万博を支えていました。
エネルギーの未来と1970年大阪万博からの歩み
1970年の大阪万博では、電力館で原子力技術が展示され、工期を短縮して福井県美浜原発1号機から万博会場に電力が供給されました。その後の原発開発は周知のとおり、2011年の東日本大震災に伴う津波で、福島第一原子力発電所が深刻な事故を起こしています。
今回の大阪・関西万博には、世界150以上の国や地域が参加し、未来の暮らし、都市、環境、医療などに対する最新のソリューションが展示されています。未病を改善する未来型住宅や、二酸化炭素を活用した人工光合成技術によるエネルギー創出といった、先進的な取り組みも紹介されています。
エネルギーの自給自足と暮らしの転換
温暖化が加速する中で空調はますます重要となり、日常の暮らしや生命を支える存在になりつつあります。このため、電力の確保と安全性の両立が大きな課題となっています。集中による大量生産・大量消費から、分散型の地産地消への転換が求められています。住宅においてはエネルギーの自給自足、つまり各家庭で電気を創り、消費する仕組みが重要になっています。
その一例が、薄くて軽く、曲がることもできる次世代型フィルム「ペロブスカイト太陽光発電」です。これまで設置が難しかった小さな屋根や壁でも発電が可能になります。積水化学工業は、会場西側の交通ターミナルの屋根にこのパネルを搭載し、大型蓄電池に充電、夜間にはバス停の照明に利用する実証実験を行っています。
万博を機に考える、未来社会と住まいのデザイン
また、大阪・関西万博のシンボルである「大屋根リング」は、世界最大の木造建築として注目されています。外径675メートル、高さ12メートルで、使用されている木材は国産材が7割、外国産材が3割です。ギネス世界記録にも認定されました。会場の動線でありながら、風雨や日差しを遮る滞留空間としても機能します。
「いのち輝く、未来社会のデザイン」。これが今回の大会テーマです。未来の社会、家族、そして住まいはどうデザインされていくべきなのか??この万博を機に、改めて考えるきっかけとしたいものです。